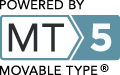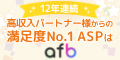スポンサードリンク
「こ、これはッ!...」 弥三はあまりの驚きに絶句してしまった。
それもそのはず、葵巴(鞆絵)は、天下の古狸、徳川家康によって幕府の権威の象徴とすべく、強烈なCI(コーポーレート・アイデンティティ)戦略を施された御紋章である。もともとは松平家が葵を御神紋とする賀茂神社を崇拝していた縁からのようだが、その葵紋の一般使用を制限し、紋を勝手に使用したり不敬な扱いをすることを禁じた。関ヶ原合戦の後もまだ方々で燻り続けている豊臣方の大名や農民庶民に対し、朝廷や天皇の紋章である菊や桐を超越する、唯一無二の権威を意識づける畏れ多きツールとして奉りあげたのだ。実際、八代将軍吉宗の時代には明文化された法令も出され、葵紋を無断使用した浪人が死罪になったという記録も残っている。ま、詳しいことは知らんけどね。
武家社会でのルールとはいえ、その畏れ多き葵の御紋に毎日小便を引っ掛けたあげく、真ん中から割ってしまったというのだから、いかに町人といえども明るみに出れば、見せしめにキツイお仕置きの沙汰が下されるのは必定だろう。二人のやもめ職人は、濡れ手に粟と喜んだのもつかの間、一転、御紋不敬の咎人とあいなってしまったようだ。
「弥三兄ィ、こりゃ公方さまの御紋...」
「明かりを消しねィ!ああ、どえらいものが出やがったぜ。留...、ま、短い間の付き合いだったが、あの世に行っても俺のことを忘れないでくんな」
「え、ええっ!ど、どういうことだよォ」
「見てみねえ、お前ェが馬鹿みたいにぴょんぴょん跳ねたもんだからよ、公方様の葵が真っ二つに割れちまったぜ。この狼藉がお上に知れりゃ獄門、いんや鋸挽の刑は免れめえ。小塚ッ原でよ」
「何言ってやがんでい!兄ィだって毎日毎日小便を引っ掛けてたんじゃないか。公方様に小便かけといて只で済むもんかい!」
「しっ...。大きい声を出すなよ。まあ落ち着け。鋸挽はこれが岡っ引きに嗅ぎつけられたらの話でい。今は幸い俺とお前ェの二人だけだ。このまま隠しちまえば分からねえ、バレなきゃどってことありゃしねえんだよ。それより先にお宝だ。それも葵の御紋付き...この際はさっさと中味を頂戴してから次の算段をしたほうが利口だぜ」
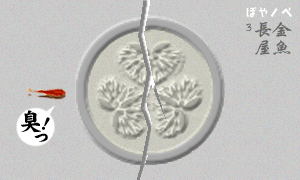
狼狽えていた留吉だが、そこは現金なもの。「お宝」を思い出したとたん我にかえった。二人は周りに気を配りながら、手早く上にある残土を取り除いて石の蓋の全てを露出させた。中央に大きく葵巴の紋章を刻んだ黒御影の矩形が闇にぼんやり浮かび上がる。無残にも紋を縦断するように一本の亀裂が走っている。
「ううむ。でかしたぞ、留」
「何だい、薮から棒に」
「この石蓋、見たところ厚みも相当ありそうだ。二つに割れてなきゃ俺達二人の力では到底持ち上げられないとこだぜ。人を呼ぶわけにはいかねえしよ」
「でも、おかげでオイラは鋸挽...あ、そうだ!弥三兄ィ、首尾よく中味を頂いたあと、この蓋を兄ィがわからないように掛け接ぎすりゃいいんだよ。兄ィの腕は評判だしよ、お茶の子さいさいだろ、あとは知らんぷりしてりゃオイラの首も安泰」
「お前ェはほんとに馬鹿だな。俺は鋳掛屋だ。鍋釜なら持って来やがれってとこだが、鋳掛でどうやって石を接ぐんだ、つうの!」
「なんでェ。石も接げない鋳掛のくせに大きな顔してんじゃねえや!ああ首が涼しいなあ。仕方ねえ、早いとこ物騒なこの公方様をどこかへ隠してしまおうぜ」
「しかしこの重さじゃそう遠くへは運べねえな。留、お前ッちの縁の下が手近だ。とりあえずそこに放り込んどくことにしよう」
割れた石蓋に両側から手を差し入れた二人は、腰を落として踏ん張り、何とか持ち上げて留吉の長屋の縁の下へ運び込む。さらにもう一片を運び終え、畳で覆って一息つくと、期待に鼻の下を伸ばしながら、手燭を手に再び穴のところへ戻った。
「さて、と。お宝はあるかな。留、穴ン中を照らして見ねえ」
「よし来た。エヘヘ、千両~箱ヤ~イ、っと」
並んで穴の奥を覗き込もうとした刹那、二人の背後から声がかけられた。
「その方ら、そこで何を致しておる」
驚いて振り返った二人の目に、長身の侍の輪郭が映った。
つづけ!