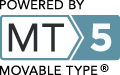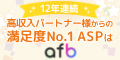スポンサードリンク
鰻の寝床の京町家
そろそろ冬の気配が感じられてきた今日この頃なので、今回は火のことを思いだしてみる。書いていることと、あたしの年齢とにギャップを感じる方がおられるかもしれないので記しておくと、生家母屋の普請自体はまま並の上なのだが、それは過去に小バブルの時期でもあったのだろう、あたしの知っている「昭和」の時期には、世帯の現金収入が乏しかったようなので、いわゆる住宅設備なんてものの改善が一般のご家庭より多少遅れていたのかもしれない。それになによりガキの頃のことである。記憶違いや年代の齟齬なども大いにあろうが、本稿は依頼原稿ではないので、いちいち裏付け調査や事実確認などしない。いたって適当いい加減に書き綴ってゆくのである。また当時の生家の周囲環境などについては、その都度新たに説明することもしないので、不可解な点は前稿をたどってみていただきたい。

さてその貧乏世帯の「似非京町屋風」家屋は、風呂のときに書いたように、家屋をタテに貫く土間があった。玄関のたたきの奥には井戸とカマド(おくどさん)のある一画があり、そのまた奥にはやや幅を細くして米櫃食器棚などを設置する廊下となり、ふたたび拡がって台所兼洗い場兼洗濯場(はしりもと)が続く。そして突き当たりが小庭に接して浴室&厠である。井戸とカマドのある区画は大黒柱があって、二階屋根までの吹き抜けになってい、小さな天窓があった。これを見ているおかげで、古典落語、「金の大黒」や「不動坊」なんかの情景はすぐに思い浮かべることができるのだ。大黒柱には「秋葉さん」のではなかったが、火除の札が貼ってあった。ただし、大店のそれと一緒にするのはとんでもない大間違いであろうが。
このカマドのスペースに接する部屋が、いわゆる卓袱台のある食堂なのだが、調理をするには奥の「はしりもと」で調製したあと、小走りに土間を移動し、カマドで煮炊きし、いちいちゲタを脱ぎ土間から一段あがって食膳を用意するという、極めて非合理な動線であったので、他所から嫁いできたヨメにとっては大変な苦痛であったろうと思う。でもまあ連日大量の段登り降り運動のおかげで、京都のヨメの足腰はかなり鍛錬されたのではなかろうか。おくどさんはコッペパン状に土盛りをした大袈裟なものであったが、その大きさにもかかわらず「二口」である。おのおのの焚き口に薪や石炭を焼(く)べて炊飯や煮炊きをした。サブにはかんてき(七輪)が活躍した。ま、今の電子レンジですな。たぶん煙突があったと思うが、換気扇がなかったのは確かだ。当時ライフラインがどう整備されたのかは調べていないが、昭和30年代の中盤あたりにひと通りの水道・都市ガスが通ったのかもしれない。あたしは幼児であったが、そのカマドの姿が退役後のみだったかどうか・・かろうじて使用されている光景も見たような気がしている。

長火鉢を抱いて余生を惰行した爺様
玄関を入ったあがり框の一室、玄関間では、いつも隠居した爺様が火鉢を前に新聞を拡げ、友人の来るのを待っていた。冬の居間や食堂には丸く大きな火鉢が置いてあったが、爺様のそれは、長火鉢である。まあ貧乏所帯であるから、骨董屋で黒光りしているような上物ではない。これも安物の似非長火鉢である。とはいっても長火鉢の機能は満たしているので、それで良かったのである。子供の目にも安物と解るような小さなものだったが、一応一丁前に銅壷も抽斗も付いてい、白い灰入れには炭が熾り、常に鉄瓶が掛かっていてコトコト音を立てていた。ガキのあたしはこの炭や灰を鉄の火箸で慣らすのが好きで、よくキセルを燻らす祖父の横に座っていたものだが、今思うに、あたしが焚火酒野宿を好きな下地は、あの長火鉢の灰いじりから来ているのだと合点した。なれば、なにも雑木林まで足を伸ばさずとも、長火鉢を購入すれば毎日、酒肴&火弄りを愉しめそうなものだけれど、サッシ付き鉄筋ボロマンション住まいではそうもいかない。当時の家屋は、木造土壁のうえカマド・天窓まである構造だからこそ安全だったのであって、今や一戸建の暮らし向きの御仁でも、煤煙による室内の汚れや一酸化炭素中毒の危険を考えると、この贅沢は無理筋なのではないか。
爺様が耄碌するとともに、炭を熾すことが難儀になり、また火の用心も危険だということで、オヤジが謀ったのであろうが、長火鉢が電熱のものに変わってしまい、長火鉢へのあたしの興味も引いてしまった。ニクロム線周囲の燠のない灰など慣らしても少しも面白くない。爺様が肝臓を患っていたこともあってか、銅壷が省略された廉価タイプだったので、味気も何もなくなったが、それでも時々は、近郊の農家が届けてくれた「かきもち」「するめ」「酒の滓」などを焙りながら、爺様とお茶を呑んだりした。この頃になると、居間の丸火鉢も、どんどん灯油ストーブや練炭火鉢に置き替わり、暖かいものの、臭いのがとても不快で堪らなかった。特に練炭火鉢は、子供心に趣の無い器具だなあと思って見ていたのを憶えている。
それらの火鉢は、法事用などの上物を含め、特大から小さなものまで十個以上はあったと思う。それだけの嵩のものを、使用しない夏場はどこに収納していたのかというと、縁の下であった。玄関間奥の床がはね上げられるようになっていて、その部分が漆喰の土間にしつらえてあり、そこにずらりと火鉢が並んでいた。この場所への収納では出し入れが面倒だと思うのだけれど、昔はちゃんと「大掃除」という行事があったので問題がなかった。歳時に、町内が一斉に行なうことで騒音や埃の苦情を無くす、といううまくした仕組みがあったので、ズボラをこくこともなく毎年キチンと出し入れができたようだ。この床のはね上げ設備だが、どうやら戦時中の、当局指導による防空壕の跡だったようである。戦後、穴を埋めてしまい物置にしたようだが、冷静に考えてみると、ここに避難しても家屋の真下の壕である。被弾して火災になった場合、逃げ場もなく蒸し焼きになるしかないアホらしい設備だと思うのだが、いったい当時はどう考えていたのか。案外、憲兵などへの言い逃れ用トマソン物件だったのかもしれない。(2004-11-04 掲載記事を復刻)